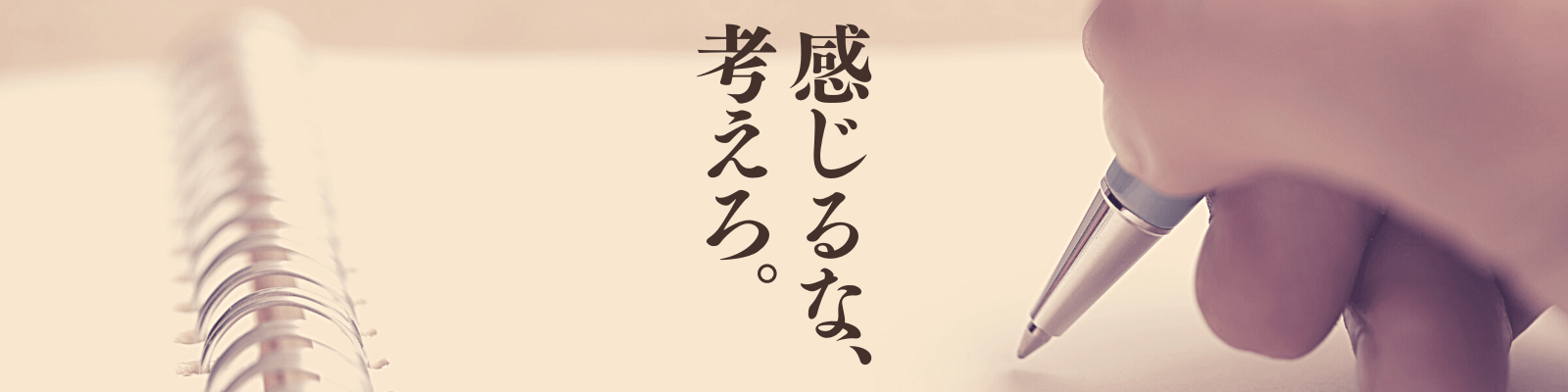久しぶりの帰国を機に健康診断にいったら、三カ月後に死ぬと言われていた。いつ死んでもいいと思って暮らしている彼にもそれは衝撃的な事実だった。彼は
「ああ、そうなんだ」
と言うともう受け入れたのか、まだ悲しんでいるのか分からないような表情だった。死を宣告した医者もその様な受け入れ方に少し驚いていた。やはり多くの人が泣き崩れるものなのだろう。
「・・・・・・。」
私は何もかけられる言葉が無く、涙を流していた。彼とは出会ってもう五年目になる。異国のインドで出会った。バンドという趣味が一緒でたまたま日本人のサークル活動で出会った。一緒に音楽をやるということは無かったが、ご飯の席やイベントの会場では何となく気が合って横に座ることが多かった。特に付き合っている訳ではないが一度だけ一緒に横で一夜を過ごしたことがある。その夜もセックスをするどころか手を握ることもなく、肌すら触れなかった。私はどちらかというと期待していたのだが、気を許している彼とただ時間を過ごすこともとても良い気持ちがする。今回もたまたま日本に帰国するタイミングが重なり、健康診断の追検査の結果を聞いた後にご飯にいく約束だった。
「俺、死ぬんだって。」
彼はいつもの様に顔面一杯をクシャクシャにしながら少し高めの声で笑いながら言った。
「うん。」
「そんな顔しないでよ~。ご飯行きましょう。せっかく赤坂の、えーっと名前忘れちゃったけどお店予約したんですから。」
「うん。」
私は彼が何を言っているのか、彼が死ぬということがまだ分かっていなかった。何も受け入れられず、ぼーっと六本木を一緒に歩いていた。
「体調悪いんですか?タクシー乗ります?」
「うん。」
言われるがままうなづいた。彼は天高く、まるで初めてタクシーを捕まえる小学生の様に意気揚々と手を挙げ、また手を振ってタクシーを止めた。
「赤坂までお願いします。あ、えっとお店の名前は」
そう言いながら彼はスマートフォンのカレンダーを開き、お店の名前を告げた。
「すみません。赤坂じゃなくて青山のカシータまでお願いします。」
私は赤坂ではないことも気が付いていたし、カシータというお店の名前も覚えていたのだが、そんなことどうでもよかった。彼が死ぬと言われてまだ十分。
「いやーすみません。ほんと昔っからもの覚えるの苦手で全くだめなんすよ。」
「うん。いや。うん。」
「大丈夫?今日辞めときますか?」
「いや。行く。」
「体調悪かったら言ってくださいね。絶対。また次回でもいいんですから。」
「次回。うん。」
彼はいつも予定が埋まっているタイプの人間で、なんで私を誘ってくれるのかは分からない。私は彼のことが気になっていて、簡単に言えば好きだ。私から彼を誘ったこともあるが、その場合はいつも仕事を理由にしたり、共通の友達が会いたいと言っているからという理由で誘っていた。もちろん本当はいつでも会っていたいし、二人で会いたいけど、そういった関係性は彼に嫌われそうで怖かった。後は彼は結婚している。浮気や不倫をするような人には見えないし、いつでもその左手の薬指にはシルバーの素朴な指輪がいた。
「でも忙しいじゃんいつも。」
「いや、まぁそこは適当に調整しますよ」
「いやいや、今日楽しみにしてたから今日行こ」
「はい!僕もめっちゃ楽しみでした。日本で会うって新鮮だね。」
六本木から青山をタクシーで移動したのは初めてで、意外と近かった。
「あーここ、ここ。お店の雰囲気も料理もお酒も働いている方も何もかもいんですよ。」
「へぇーそうなんだね。」
私は彼の“働いている方”という丁寧な表現がとても好きだ。どんな人にも対等に、オープンに接することができる彼を本当に尊敬している。
「いやーでもまいっちゃったな。後三か月か。」
「うん。」
彼は入学試験の残り期間かの様な調子で平然と言った。
「もし後三か月しか生きられなかったら何しますか?」
「え?私?」
「うん!何します?」
三か月という期間がより具体的に思えてきて私はまた涙を流してしまった。
「あ、すみません。」
「いやいや。こちらこそ。」
「三か月ってなんか微妙に長いんですよね。」
「短い!」
私はつい取り乱してしまった。
「あ、そうですよね。ワンクオーターですもんね。んーでも僕は今やってることを変える積りはあまりないなぁ。自殺することを考えたり、逆に無気力だったりしたこともあって、その上で今やりたいことをやってきてるからなんか後悔したことなんて一つもないし、これからも変わらない。」
「うん。そうなんだね。」
二人の前にウイスキーが来た。彼はいつも一杯目はビールだった気がするのだが、今日はなぜかウイスキーを頼んでいた。こんなことに気が付けるぐらいには私も正気を取り戻していた。
「おつかれっす。」
「うん。」
お疲れ様なんて言いたくない。まるで人生今までお疲れ様でしたと伝えているような感覚になりそうだ。そんなことを想うと余計に涙が落ちてきた。せっかく張り切って直した化粧も台無しだ。
「あーうまい。なんで一杯目ってこんなうまいんすかね。これがずっと続けばいいのに。」
「うん。」
「そういえばいつまで日本ですか?」
「来週帰るよ。」
「そうなんですね。僕はまだ一か月もあるんですよ。早く帰りたいんですけどね。」
何が一か月“も”だ、そんな言葉使わないでよ、と心で泣きながら叫んでいた。
「なんか日本いると静かすぎて疲れちゃうんですよね。静かで疲れるってなんか矛盾してるみたいに聞こえますね。ははは。」
彼は勝手に笑っている。彼は結構自分のことをたくさん話す。彼のことをいろいろと知れてとても嬉しくなるが、たまには私のことも聞いて欲しいと思う。だいたい来週帰ることは今日会った時にも聞いてきたのに完全に忘れている様子だった。
「日本はずっと東京にいるの?」
「はい。その積りです。ただ日本円の収入が無いとつらいですね。」
「そうだよね。東京っているだけで高いもんね。」
「そうなんですよ。家賃はまだわかるとして、なんかお金使っちゃうんですよね。いろんなことに。」
「わかるわかる。」
「あれって何なんでしょうね。東京だけなんですかね。」
「どうなんだろうね。少なくとも実家と東京しかいないからそりゃそうだよね。」
「たしかに。」
「今回は実家に帰ったんですか?」
「うん。帰ったよ。」
「どのくらいですか?」
「んーっと。一週間ぐらい。」
「あ、じゃあ結構ゆっくりできたんですね。」
「うん。」
「地元の友達に会ったり。」
「うん。会ったり会わなかったり。」
「そりゃそうすね。会っている人がいりゃ会わなかった人もいるでしょうね。」
「うん。ん?うん。」
「日本から帰る時って何買って帰ってます?」
「んー、とりあえずラップと歯ブラシと出汁は」
「なんですかそれ?」
「え?だってラップは買えないし、歯ブラシはすぐ壊れるし、出汁が無いと料理できないし。」
「僕は歯ブラシはなんでもよくてその辺の五本で五十円ぐらいのやつで他の二つは全く使わないっすね。」
「料理する時間ないもんね。」
「いや、普通にできないっす。」
「え、でも奥さんは?」
「あー奥さんはしますよ。たまに。そういや出汁買ってこいって言ってたな。」
「でしょー。出汁ってめっちゃ重要だからね。」
「そうなんだ。何かあんま味分かんないからわかんない。」
彼がたまにタメ口になるのはとても好きだ。彼は三十歳で私はちょうど十歳年上だから彼は普段、敬語を使っている。でも敬語の中にたまにタメ口があるから好きだと感じるという感じもする。でもやっぱりいつもタメ口で話してもらいたいような気もする。彼はいつもと変わらず、なんでもないような会話を本当に楽しそうにしていた。三か月の命だと言われたその日にも何も変わらずに。なんでだろう。
「僕実はあなたのこと好きです。」
「うん。」
「・・・・・・」
「え?・・・・・・ええええ??・ん?」
「好きなんです。」
彼はいつもふざける時に“あなた”という二人称で呼んでくる。
「僕は結婚していて関係性をどうこう言う積りはあまり無いですし、もちろん苦しい思いをしてほしくもないですが、どうしても伝えないと気がおかしくなってしまいそうで、ここ最近。」
「・・・・・・」
「特に付き合って欲しいとか、結婚したいという訳ではなく、今の感じのままでも、ままでもというか、この感じもとても心地よいんです。でもそうして欲しいということでしたら離婚をしてもいいと思っています、」
「・・・・・・うん。」
忙しい日だ。好きな彼が三か月後に死んでしまうことが分かり、その同じ人から告白(?)されている。
「僕の気持ちは好きという想いが強くて、ただ、だからどうこうっていうのは無いんです。」
「うん。私はどうしたらいいのかな。」
心の声が漏れてしまった。
「困らせちゃいますよね。すみません。」
「あ、いや。嬉しい。だけど。」
正直私も今までの関係のままで結構満足していた。もちろんセックスもしたいし、毎日おはようと言い合いたい。でも今の関係もすごく好きだった。誰も一線も越えてないけど彼には会える。そんな関係がとても心地良かった。私から好きと言わなかったのは、関係がおかしくなってしまうことがとても怖かったからだ。
「うん。大丈夫。私も好き。というか大好き。」
正直もう頭は働いてなく、でも正直に、関係がどうなろうと覚悟して言おうと思って言った。
「ありがとうございます。」
彼はその二ヶ月後に死んだ。医者が言うより早かった。私が彼の死を知ったのは死んでから三か月も後になってからだった。私は日本から戻っており、彼のツイッターやフェイスブックをチェックしてあんまり更新してないから気になっていた。でも彼がどうなっているのか確かめる方法が無かった。彼に直接連絡をしたのは死んでから二カ月後。もともと死ぬと言われていたその月に連絡をするのはあまりに怖かった。どちらにせよ連絡は返ってこなかった。いつもならすぐに連絡を返す彼から連絡が無い日が続いた。私は不謹慎だとは思っていたが、どうしても抑えきれずにフェイスブックの彼の家族に登録している彼のお兄さんへ連絡をした。お兄さんからはとても丁寧な文面で、連絡をしたことに対するお礼と、死んでしまったことが書かれていた。その後お兄さんへ返信することもできずに私は異国の一人暮らしの部屋で声を出して泣き、想いだすたびにいつも泣いた。一緒に検査結果を取りに行ったあの夜も、その後も私たちの関係はずっと変わらなかった。彼は小説の中の人みたいで、時間が流れずに紙の上に残された文字の様に関係をずっと保っていられるのかもしれない。そこにずっといる方法を知っていたのかもしれない。死んでしまった。私の中でも生きていない。生きてなんかいない。思い出したくても彼の匂いを想いだせないことが悔しい。
「おはよう。」
たった一度だけ見られた寝起きの顔のまま、毎日誰もいない一人の部屋でつぶやいている。